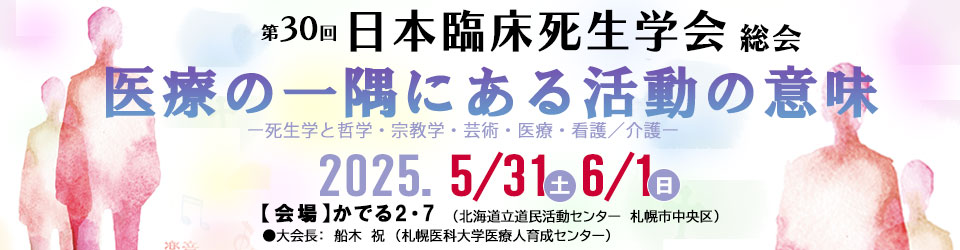
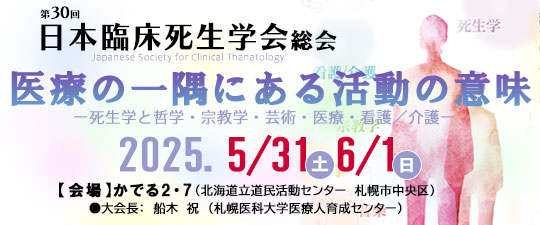
医療の一隅にある活動の意味――死生学と哲学・宗教学・芸術・医療・看護/介護
臨床死生学会の設立趣旨には、「人間の生命は有限であり,病気や死に伴う恐怖や不安,悲しみ,死別による悲嘆といったものは,たとえどんなに医学が進歩しようともなくなるものではなく,先端技術に裏打ちされた医療にはより一層の精神面への配慮が求められてくる」とあります。第30回日本臨床死生学会大会は、「科学的エビデンスの側からは遠く(もしくは対極)にあるような、哲学、宗教学、また芸術、積極的治療と並行しておこなわれる緩和医療、慢性疾患や認知症や意識のない患者に対する看護/介護などの活動が、医療・福祉においてどのような意味があるのかを問う」ことをテーマにします。
最先端の専門知識に則って診断と治療に携わる、医科学的知識・技術に基づく医療は、標準を決定する医療における舞台の主役です。しかし、医療・福祉の現場において、そして医療・福祉の恩恵を受けている/受けるだろう市民に対して、医療者だけではなく、さまざまな人々が多様な活動をおこなっています。表舞台では、解決のない問いを追い続ける哲学は、迅速に決定することが求められる医療現場では、足かせになると考えられています。中立の立場ですべての患者に公平に接しなくてはならない医療者にとって、宗教性/スピリチュアルな側面への目配りはどうしても後退せざるを得ません。音楽やアートなどの芸術は、病気や死に伴う恐怖や不安を和らげる効果がある可能性があったとしても、その意味は明確とされていません。医学的には治療効果のない患者や、意識のない患者に対する終末期医療や看護/介護などの活動は、全く無意味なものでしかないのでしょうか。
人間はあらゆる生物の中で、唯一意味を問うことのできる存在です。意味への問いは、意味がないとされることへの反転の問いです。もし、意味がないとされるならば、精神面でのケアが後退したり、十分な、多角的な議論がされないまま安楽死正当化への道が加速することになりかねないでしょう。
戦後の医療政策は、戦争犯罪への反省を基礎に形成されてきました。医療は最終的には市民のためにあります。それぞれ多様な価値観を持った市民の意向に添えなくては、医療の母体が危ぶまれていきます。医療の一隅に位置づけられがちな、さまざまな活動の意味を今改めて問い直すことが、医療の将来を画一的な一元化の方向にではなく、豊かな多元化の方向に推し進めていくと考えます。

2025年1月6日
第30回日本臨床死生学会総会
大会長 船木 祝
(札幌医科大学医療人育成センター)